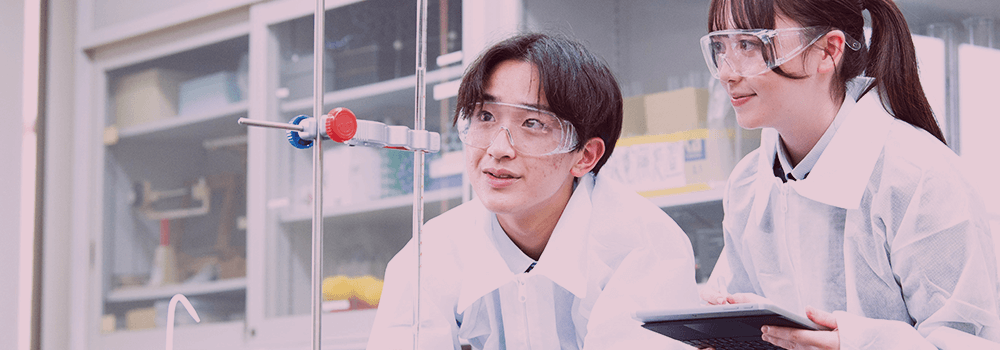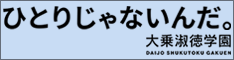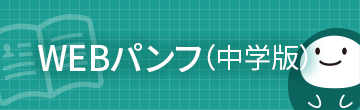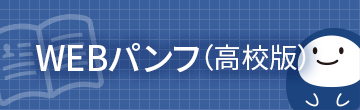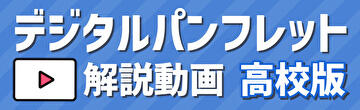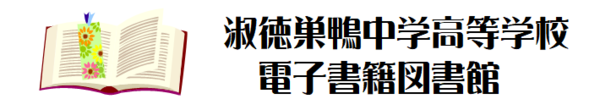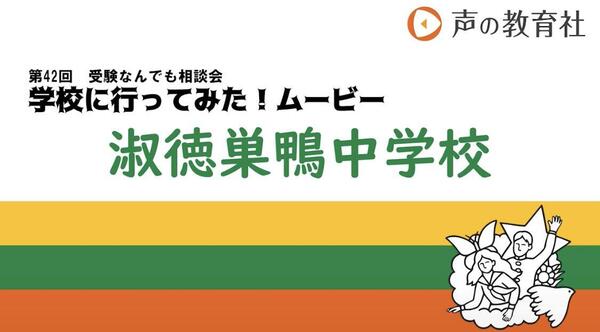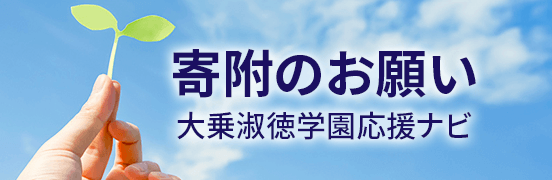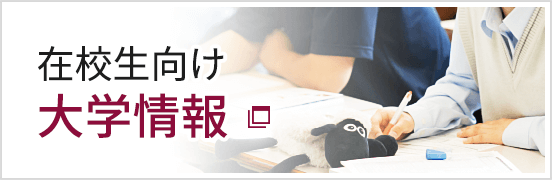校訓 感恩奉仕

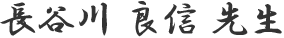
宗教・社会福祉・教育を三位一体とし、人間開発・社会開発に生涯を捧げた社会事業家。
長谷川良信先生は、学校を創立する際、根本の教育理念を「感恩奉仕」という言葉で表されました。「感恩」は、自分を取り巻くすべての存在に"ありがとう"と感謝をする心です。人や物、空気、水などが存在することをあたりまえと考えるのではなく、その"おかげさま"で生かしていただいているのだと気づいてほしいという願いが込められています。「奉仕」は、自身が身につけた能力を、世の為、人の為に生かした生き方をすることです。「奉仕」と聞くと、寄付や身体を動かす奉仕活動を連想しがちですが、必ずしもそれだけではありません。日頃簡単にできる奉仕は身の回りに溢れているものです。例えば、毎朝明るい声で"おはよう"と挨拶すること、優しい笑顔や言葉で人に接すること、これらすべてが「奉仕」なのです。
沿革
| 1919年(大正8年) | 優れた宗教家であると同時に、日本の社会事業の先覚者としても知られている長谷川良信先生が、西巣鴨のスラム街に身を投じ、貧困な人々を教化、救済する活動(セツルメント)として、社会福祉施設「マハヤナ学園」を設立する。 |
|---|---|
| 1924年(大正13年) | 男子尊重が残る風潮の中で、貧しさからの解放は“自立した女性の育成”にあるとし、教養ある社会人、職業人として活躍することのできる“商業・経済”の専門知識技術を修得させる目的で、マハヤナ学園内に夜学の「大乗女子学院」を開設する。 |
| 1925年(大正14年) | 大乗女子学院を発展的に改組し、「巣鴨家政女学校」となる。 |
| 1931年(昭和6年) | 東京で最初の甲種商業学校として認可を受け、校名を「巣鴨女子商業学校」に変更する。 |
| 1948年(昭和23年) | 新学制により、校名を「巣鴨女子高等学校」に変更し、都内の名門女子商業学校として高い評価を受ける。 |
| 1950年(昭和25年) | “浄土宗教育資団淑徳”と合併し、「学校法人 大乗淑徳学園」が形成される。 |
| 1955年(昭和30年) | 校名を「巣鴨女子商業高等学校」に変更する。 |
| 1973年(昭和48年) | 時代のニーズに応えるために、商業科に加えて普通科を設置し、校名を「巣鴨女子高等学校」に変更する。 |
| 1979年(昭和54年) | 職業教育は普通科の中においても実施できるという考えから、商業科を廃止して普通科の高等学校となる。 |
| 1985年(昭和60年) | 校名を現在の「淑徳巣鴨高等学校」に変更する。 |
| 1992年(平成4年) | 21世紀への教育をめざし、男女共学校となる。 |
| 1996年(平成8年) | 中高一貫教育のために「淑徳巣鴨中学校」を開校する。 |
| 2003年(平成15年) | 最新の設備と機能を持つ校舎(地上7階、地下1階)が完成し、教育環境が設備される。 |
| 2019年(平成31年/令和元年) | 創立100周年を迎える。 |