気づきの結晶が今、輝く
受験期が辛くても大学で何を学びたいかを想像して自分を奮い立たせました

S.Hさん
2024年卒業生
帝京大学 医学部医学科進学
小さい頃にお世話になっていたこともあり、将来は小児科医になりたいと考えています。その夢を叶えるべく受験勉強も早期から取り組んでいましたが、高3の夏頃は成績が振るわず悩むこともありました。そのような時、担任の先生から「受験は楽しんだ者勝ちだよ」とアドバイスされ、心が少し楽になりました。そして苦手科目である化学を克服しようと切り替え、単元ごとに基本問題から取り組み、過去問もきちんと理解するまで時間をかけて解くように心がけました。合宿勉強会では一緒に励んだクラスメイトにも良い刺激をもらい、辛い受験期を乗り越えることができました。淑徳巣鴨での6年間を振り返ると、先生たちや仲間にとても恵まれていたと思います。私は内気で自分の意見を言うことが得意ではなかったのですが、イギリス修学旅行に向けてプレゼンテーション練習をするうちに人前で話す勇気が身につきました。受験勉強も含めて、苦手なことでも頑張った分だけ自分に還元されたことは、淑徳巣鴨で過ごす中で得た大きな成功体験だと思います。
日々コツコツ努力すること積み重ねの大切さを淑徳巣鴨の6年間で教わりました

M.Kさん
2025年卒業生
お茶の水女子大学 文教育学部進学
物事を後回しにしがちな私ですが、淑徳巣鴨では日々コツコツと頑張れることがありました。それは、毎朝の「朝テスト」と「NPU」です。朝テストは、英単語や古文単語、漢字などの習熟を目指す小テストで、NPU(News Pick Up)はニュース記事を読み、自分の考えを作文します。このおかげで、頭の中の引き出しを増やすだけでなく、読解力や作文力も伸ばすことができました。気づけば毎日の地道な勉強が習慣となり、受験対策においても、迷うことなく着実に勉強を進めることができました。もともと国語や英語が好きで、辞書を読み込むうちに言葉の構造や意味の広がりが楽しくなり、言語文化学科を志望するようになりました。苦手だった数学も、受験直前まで諦めず頑張った結果、良い成績を取ることができたのです。この経験から「得意不得意ではなく、どれだけ頑張ったかがすべて」だと実感。努力は決して裏切りません。「塵も積もれば山となる」の言葉通り、日々の積み重ねが大きな力になることを、淑徳巣鴨で学ぶことができました。
一つのことを極めていけば自分でも考えていなかった世界が広がっていきます

Y.Yさん
2025年卒業生
慶應義塾大学 文学部進学
私は中学から淑徳巣鴨に入学し、特進コースで6年間を過ごしました。入学理由はシンプルで、バドミントンを続けるため。小学2年生から始めたバドミントンは私の生活の中心で、中高6年間は全国大会に出場するほど打ち込みました。高3の夏、大きな転機が訪れました。慶應義塾大学に通うOBから「バドミントン部で部員を募集している」と聞いたのです。それまで明確な進路は決めていませんでしたが、「バドミントンを続けたい」という思いから、慶應義塾大学を目指すことを決意。8月に部活を引退してからの半年間、猛勉強の日々が始まりました。英語、国語、小論文を中心に過去問を解き続け、特に配点の高い英語は担任の先生に添削してもらいながら力をつけていきました。6年間を振り返ると、「部活に行きたくない」と思う日もありましたが、「バドミントンのために淑徳巣鴨を選んだ」と自分に言い聞かせ続けてきました。その結果、ひとつの道を突き詰めたからこそ、慶應義塾大学進学という新たな可能性が開けたのだと実感しています。
先生と友人のサポートで苦手科目が得意になったとき見える景色が変わってきました
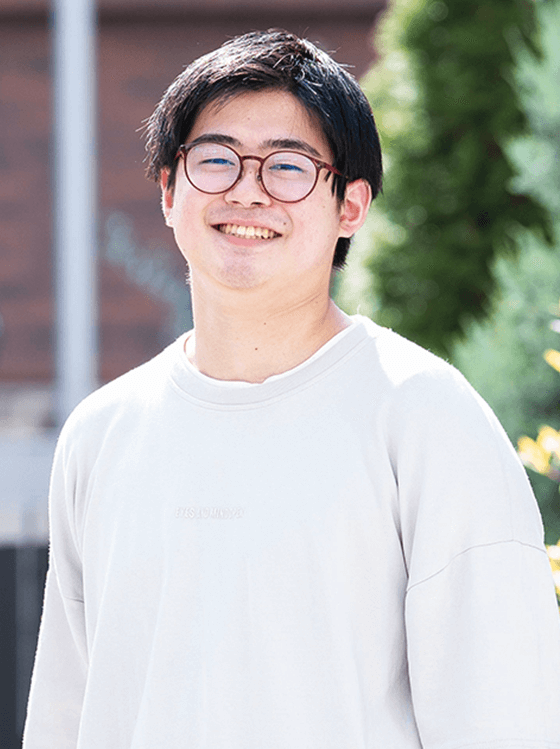
E.Kさん
2025年卒業生
北海道大学 総合教育部(理系)進学
僕は中1の頃からバドミントンに打ち込んできました。バドミントン部と勉強を両立することは簡単ではありませんでしたが、日々の授業をきちんと受けることと朝テストの勉強を欠かさずにすることで、基礎力を維持していました。ところが、高2の秋から急にスランプに陥り、勉強も部活も思い通りにならない苦しい時期となりました。その時に本当に支えになったのは、先生方と友人のサポートです。家にいても「Teams」のチャットで質問すれば先生が答えてくれるので、自習を効果的に進めることができました。学校では友人と他愛ない話をして笑い合うことで、沈みそうになる気持ちを立て直すことができました。家族をはじめ、自分を支えてくれた色々な人たちにとても感謝しています。淑徳巣鴨での6年間で特に印象に残っているのは、「嫌いだった科目を好きになる」という経験です。小学生の頃は算数が一番苦手な科目でしたが、中学で受けたわかりやすい数学の授業のおかげで、いつの間にか数学が好きになり、得意科目になりました。その結果、大学でも数学や物理の分野に進みたいと思えるようになったのです。「シンクタンクで働き、社会課題を解決する人材になりたい」という目標を胸に、大学での勉強も頑張っていきます。




